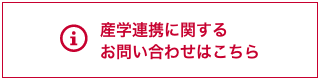東邦大学、千葉大学、東洋食品研究所の研究グループは、外来性巻貝サキグロタマツメタ(図1)の環境DNA(sedimentary DNA、以下、sedDNA)(注1)を堆積物中から検出する方法を開発しました。
サキグロタマツメタは中国や朝鮮半島の沿岸を原産とするタマガイ科の巻貝であり、輸入された外国産アサリと共に日本国内に侵入し、分布を広げています。また、本種は生きたアサリを好んで捕食することから、食害生物として広く認知されています。さらなる分布拡大や食害を抑えるためには効率的に駆除していく必要があります。しかし、本種は干潟の堆積物中に潜っていることが多く、目視で生貝を発見することは困難でした。つまり、私たちの“見えないところ”で食害が進行しているのです。
そこで研究グループは、海洋堆積物中のsedDNAに着目しました。sedDNAは約1 gの試料で分析が可能であり、特定の生物がその環境に生息するかどうかを推定することができます。本研究では、堆積物中からサキグロタマツメタのDNAのみを検出する種特異的分析法(注2)の開発を試みました。具体的には、サキグロタマツメタのDNAのみを検出できるプライマー・プローブ(注3)を設計した後、滅菌した珪砂を入れた水槽内でサキグロタマツメタを飼育し、珪砂中からsedDNAを検出できるかどうかを検証しました。
その結果、10サンプルの珪砂うち9サンプルからサキグロタマツメタ由来のsedDNAを検出することに成功しました。また、sedDNAの濃度(単位はcopies/g sediment)測定をしたところ、濃度は106 ~ 108 copies/g sedimentでした。先行研究の多くは魚類を対象としていますが、検出されたsedDNAの濃度は102 ~ 106 copies/g sedimentの範囲に収まることが一般的です。つまり、サキグロタマツメタは非常に高い濃度のsedDNAを生成する可能性が高いといえます。今後はこの検出方法を野外試料に適用し、サキグロタマツメタの分布範囲をより正確に推定できる方法の開発を目指します。正確な分布範囲が推定できれば、これまで以上に効率的に駆除活動を行うことが可能になり、新たなアサリの食害防止策になることが期待されます。
この研究成果は2025年7月18日に沿岸環境科学系の国際誌である「Estuarine, Coastal and Shelf Science」に受理され、7月19日にオンライン上で先行公開、10月15日に本公開されました。
◆ 用語解説
(注1)環境DNA (sedimentary DNA:sedDNA)
水や堆積物中などの環境中に含まれるDNAの総称。生物の組織片や糞、粘液などが主なソース。堆積物中に含まれる環境DNAはsedimentary DNA(sedDNA)と表す。
(注2)種特異的分析
環境DNA分析には、特定の生物種のDNAのみを分析する「種特異的分析」と、サンプル中に含まれる様々な種のDNAを網羅的に分析する「網羅的分析」がある。
(注3)プライマー・プローブ
プライマー:DNAの特定の領域をPCR増幅させる際に使用する一本鎖のDNA断片。
プローブ:定量PCRにおいて使用される特定の塩基配列に結合するDNA断片。蛍光色素を含んでおり、PCR増幅時に蛍光を発することで、その強度から目的のDNAの濃度を測定できる。

プレスリリース本文はこちら